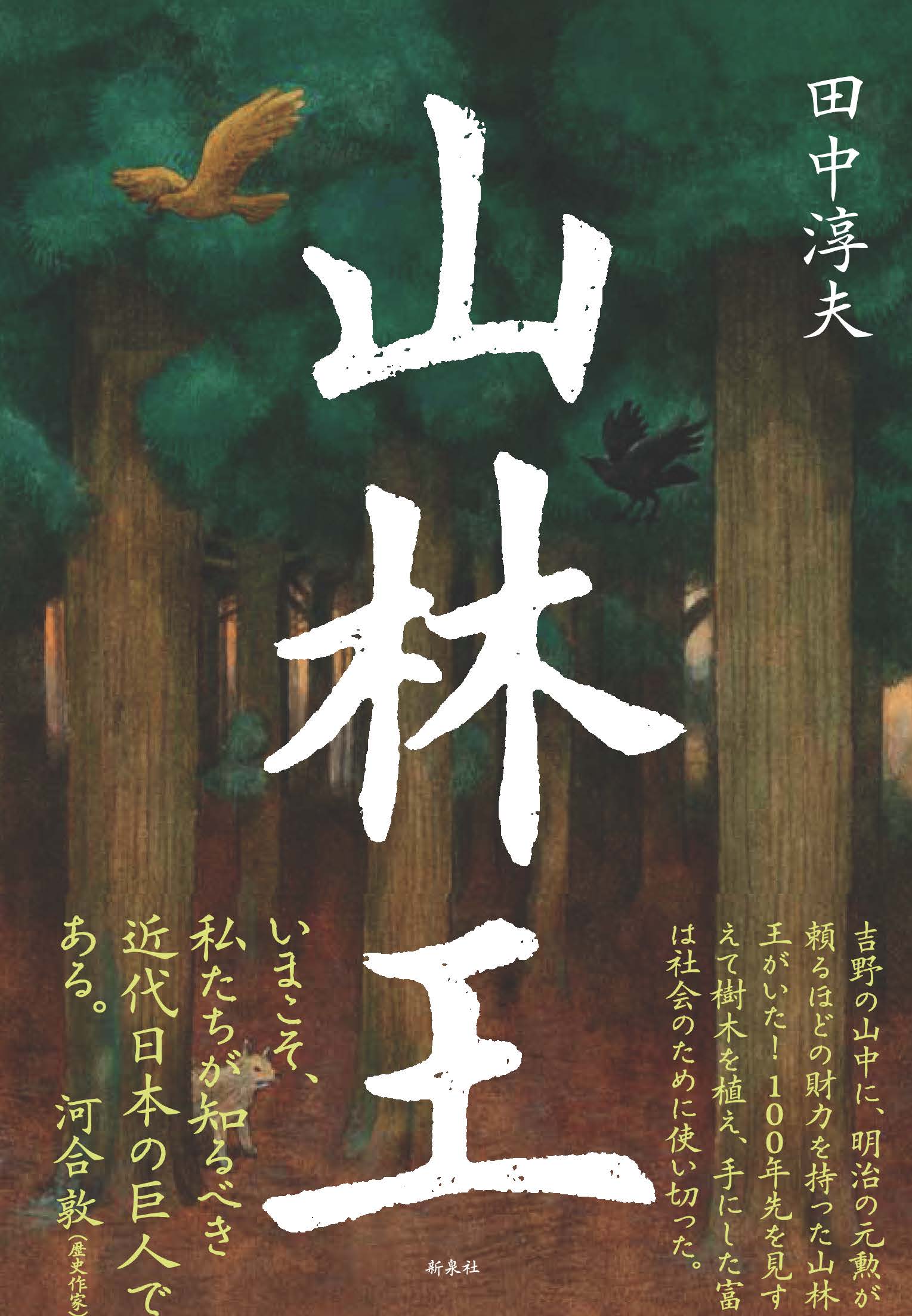
近代日本の巨人・土倉庄三郎の生涯
山林王
- 四六判
- 320頁
- 2500円+税
- ISBN 978-4-7877-2210-2
- 2023.03.25発行
- [ 在庫あり ]
- 書店サイトへ
書評・紹介
紹介文
吉野の山中に、明治の元勲が頼るほどの財力を持った山林王がいた!
土倉庄三郎。100年先を見すえて生涯1800万本の樹木を植え、
手にした富は社会のために惜しげも無く使い切った。
いまこそ、私たちが知るべき近代日本の巨人である――河合 敦(歴史作家)
明治の初め、吉野山の桜を全部買い取った男がいた。彼の名は土倉庄三郎。吉野から伊勢まで懸崖の山々を抜ける道を独力で開き、全国の山を緑で覆うべく造林を推し進め、自由民権運動に参画し、同志社など多くの学校を資金面で支えることに力を注いだ。また女子教育こそが国力を伸ばすとして日本女子大学校(現・日本女子大学)の創設を支援し、自らの娘もアメリカに留学させた。そのほか手がけた偉業を数え上げたらきりがない。吉野川の源流部・川上村に居を構え、近代日本の礎づくりに邁進した豪商三井と並ぶ財力を持った山林王であった。ところが現在、土倉庄三郎の名前は歴史から消え、彼の事績は忘れられつつある。
土倉家に起きた悲劇とは何なのか。そして吉野の山中からどんな世界を見ていたのか。彼の足跡を追いながら、幕末から明治、そして大正にかけて日本がたどった道のりを森からの視点で探っていく。
目次
奈良県川上村地図
土倉家家系図
序 源流の村へ
第1章 キリスト教学校と自由民権運動
1. 同志社の新島襄
2. 雪の峠の向こうの土倉邸………
3. 自由民権運動の台所
4. 板垣退助、謎の洋行費
5. 女性運動家景山英子
6. 金玉均と朝鮮侵攻計画
7. 国政選挙立候補の顚末
8. 新島襄の死と八重
9. 広岡浅子と日本女子大学
第2章 山の民の明治維新
1. 吉野の山々と敗者の系譜
2. 出自は楠木正成か山賊か
3. 頭角現した宇兵衛事件
4. 若き日の林業修業
5. 明治維新の税金撤廃運動
6. 二人いた「庄三郎」
7. 土倉家の力の源泉
第3章 新時代を大和の国から
1. 買い取った吉野山の桜
2. 洋服を着た小学生たち
3. 東熊野街道の建設
4. 秘境・大杉谷の土倉道
5. 大台教会の「土倉の間」
6. 大和の養蚕は川上村から
7. 古社寺が国宝になるとき
8. 十津川水害の移住事業
第4章 国の林政にもの申す
1. 本多静六の見た森林事情
2. 林業の要は搬出にあり
3. 日清戦争と年々戦勝論
4. 博覧会に出展した巨大筏
5. 『吉野林業全書』の刊行
6. 国に突きつけた『林政意見』
7. 大日本山林会の吉野視察
8. 奈良公園につくった美林
9. 全国のはげ山を緑に
第5章 土倉家の日常と六男五女
1. ミルクを飲む洋風生活
2. 長男鶴松の教育
3. 台湾に渡った龍次郎
4. 政子のアメリカ留学
5. 娘たちの華麗なる結婚
6. 亀三郎・四郎・五郎・六郎
7. 川上村の村長に就任
8. 『樹喜王』還暦の大風呂敷
第6章 逼塞の軌跡と大往生
1. 六郎の死がもたらす影
2. 在家の大谷光瑞
3. 鶴松、痛恨の事業
4. 孫たちが見た翁の日常
5. 庄三郎、最後の造林
6. 後南朝にかけた誇り
7. 死して名を残さず
終章 庄三郎なき吉野
1. 鎧掛岩に巨大磨崖碑
2. カーネーションと西太后
3. 吉野ダラーと伊勢湾台風
4. 「守不移」の人
あとがき
年表
参考文献
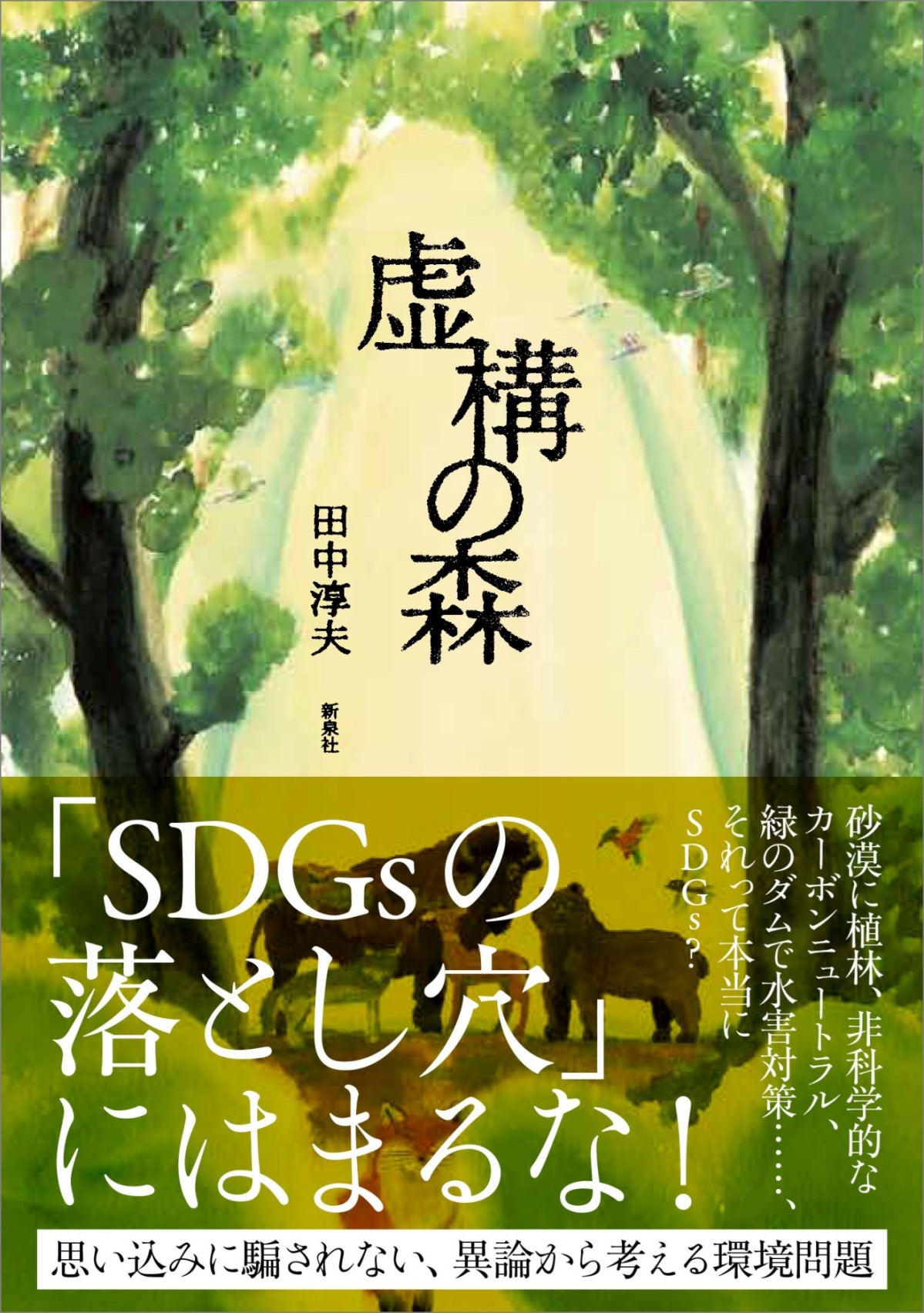
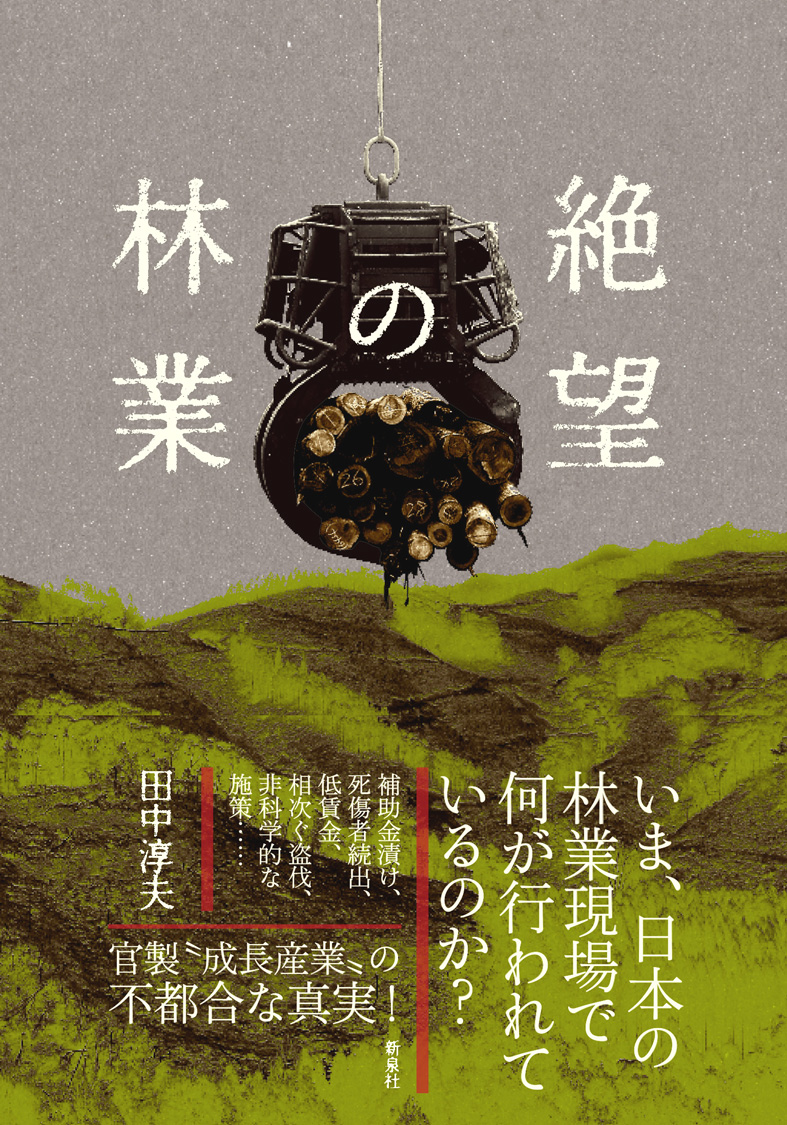
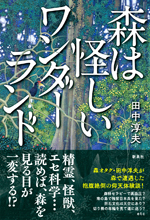
出版社からのコメント
明治という時代は多くの偉人を生みました。
明治維新の立役者だけでなく、近年、TVドラマや小説で取り上げられて有名になった人もいます。例えば、渋沢栄一、新島襄、五代友厚、大倉喜八郎、岩崎弥太郎・・・・・・。しかし、そこに土倉庄三郎の名前が挙がることは、ほぼありません。それはなぜなのでしょうか。
1843年、奈良県吉野の奥山に位置する川上村に生を受けた庄三郎は、森づくりを通して、近代日本の礎づくりに尽力しました。
当時は、豪商三井家とも肩を並べるほどの財力を持っていたことから、板垣退助の洋行費用を出したり、新島襄はじめ、多くの運動家や志ある者に資金を提供したり、朝鮮からの亡命政治家を援助したり・・・・・・と、そのパトロンぶりは驚くばかりです。
さらには吉野と三重を結ぶ道路を作り吉野林業の発展に尽力しただけでなく、日本中の山を植林するなど、日本の近代林業の基礎を作った人でもあります。「日本の林学の父」とも言われる林学者の本多静六が、林業を学びにしばしば庄三郎のもとを訪れてもいました。
そして、明治の元勲・山縣有朋から「樹喜王」という称号までもらったほどの人物でした。
そんな偉人の名前がなぜ歴史上から消えてしまったのでしょうか。土倉家を襲った悲劇とは何だったのでしょうか。
森林ジャーナリストの田中淳夫さんが土倉庄三郎の足跡を追いかけ始めてから、かれこれ17年になります。最初の本『森と近代日本を動かした男 山林王・土倉庄三郎の生涯』を書いてから、田中さんのもとには次々と土倉庄三郎に関する情報が寄せられました。それに伴い新たな資料も発見され、さらには子孫の人たちとつながることもできました。
前著刊行から10年が経ち、そうした新しい情報や写真を盛り込んで全面的に書き直したのが本書です。歴史作家・歴史研究家の河合敦先生からも「いまこそ、私たちが知るべき近代日本の巨人である」という帯文をいただきました。本書が土倉庄三郎の名前を知るきっかけになればと思います。